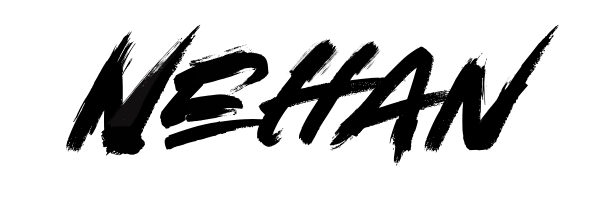みなさんこんにちは、涅槃ぶろぐのモロです。
今回は子どもの叱り方についてお話していきたいと思います。
みなさんは子どものしかり方について悩むことがないですか?
子どもが言うことを聞いてくれないとか、必要以上に怒ってしまうとか。
私の経験によるお話にはなりますが、誰かの参考になれば幸いです。
「怒る」と「叱る」の違い

「怒る」と「叱る」という言葉がありますよね。
タイトルでは「叱る」という表現をベースに書いています。
そもそも「怒る」と「叱る」についてはどのような違いがあるんでしょうか?
ネットで簡単に検索してみたところ
「怒る」は相手に自分の感情をぶつけること
「叱る」は相手を正しい方向に導くこと
という違いがあるようです。
意味合いで見ると結構違いますよね。
普段子どもと接しているとイライラすることも多々あると思います。
「人に迷惑をかけた」
「人を傷つけてしまった」
「ものを壊した」
子育てにはトラブルがつきもので、それに伴う責任は親がとります。
子育ては思い通りにいくことの方が少ないですし、イライラしてつい怒鳴ってしまった…なんて経験もあると思います。
(私はあります)
ちなみにこの「怒鳴る」というのは怒るに分類されそうですよね。
感情的になって相手の行動を咎めるやり方です。
私自身、子どものやってことに大してとっさに怒ってしまうこともあります。
こういう時は後々かなり後悔するのですが、「怒る」だけでは終えないようにしています。
これは一体どういうことなのかというと、「しっかり理由を説明してなぜ今の行動を問題視しているのか」を伝えるようにしているんです。
先ほど「怒る」と「叱る」についての違いをざっくりと説明しましたが、
考え方として「怒る」というのは自分軸で、「叱る」というのは相手軸なんですよね。
怒る:自分が気に入らないから。自分の感情に任せて非難する。
叱る:相手を正しい方向に導くため。相手の今後のために問題のある行動について知ってもらう。
くらいの違いがあります。
「怒る」が子どもに発達に与える影響

「怒る」と「叱る」に違いがあることはわかってもらえたかと思いますが、「怒る」と子どもにどんな影響を与えるのでしょうか。
まず豆知識的なものになるんですが、人は怒られ続けると精神疾患になる確率が上がります。
(これについては「精神疾患 原因」とかで調べると出てきます。)
精神疾患の発生要因として「ストレス環境」というものが挙げられるのですが、これは大人も子どもも同じなんですよね。
子どもに対して「怒る」という動作をベースとして悪い行いを非難し続けたとき、そのストレスは計り知れないものだと思います。
自分が普段生活している環境に強いストレス要因があるわけですから精神の発達を妨げてしまうリスクをかなり孕んでいるんですね。
「怒る」という動作がもたらす影響を、「将来」の視点で考えてみましょう。
まず前提として「怒る」というのは「自分の感情に任せて相手の行いや相手を非難すること」だと思ってください。
たとえば、テレビを見ながら牛乳を飲んでいた子供が牛乳をカーペットにこぼしてしまった。という状況をイメージしてみたいと思います。
「テレビ見ながら飲んじゃダメって言ってるでしょ!」
「何回言ったらわかるの!?」
「これはあなたが掃除をするの?掃除が大変なんだよ!?」
「もうあなたはテレビ禁止ね!」
これがいわゆる「怒る」というやつです。
それぞれの発言の裏には親の都合が隠れていることがわかると思います。
「テレビ見ながら飲んじゃダメって言ってるでしょ!」→(どうせこぼすんだから…)
「何回言ったらわかるの!?」→(言ったばかりなのに…)
「これはあなたが掃除をするの?掃除が大変なんだよ!?」→(やることもいっぱいあるし、また余分な仕事が増えた)
「もうあなたはテレビ禁止ね!」→(仕事増やされるし、ほぼいやがらせ)
これらについて別の理由や、いろんな感情が想像できるかと思いますが、基本的には「親視点」でしか無いことに気が付いたでしょうか?
これらの発言を振り返った時に「相手を導く要素」というものは感じられないですよね。
問題行動ではあったのかもしれませんが、「子ども視点」が完全に抜けてしまっていると思います。
では次に「子ども視点」をイメージしてみたいと思います。
「テレビ見ながら飲んじゃダメって言ってるでしょ!」→(なんでダメなの?)
「何回言ったらわかるの!?」→(何度も言われているけどテレビがおもしろいと気付いた時にはこうなっていたんだ)
「これはあなたが掃除をするの?掃除が大変なんだよ!?」→(確かにいつもママが掃除をしてくれているけど…)
「もうあなたはテレビ禁止ね!」→(なんで!?もっとテレビが見たい!!)
想像でしかないですが、こんな感じでしょうか。
子どもには子どもの言い分がある。ということと、根本的に子どもはまだまだ集中力や自身の行動を抑制する力が発達し切っていないんですよね。
大人でも行動の抑制というのは難しいと思います。
「ダイエットしているのにチョコ食べちゃった(笑)」とかあると思います。
日常的に怒られ続けた場合、子どもの立場からすると「理由もわからないまま、ママに怒鳴られた」という感覚なんですよね。
例えばそれが10年続いたらどうなるでしょうか?
自分がやることなすこと理由もわからないまま怒鳴られる10年は、十分にその人から自信や自己肯定感を奪ってしまうと思います。
子どもからすると「なんの悪気も無くやっていた行動」についてはっきりした理由もわからないまま怒鳴られるという感覚だと思います。
「自分は無意識のうちに悪い行動をとってしまい、良し悪しの判断基準もよくわからない」という状況を生み出してしまうんですよね。
ちょっと極端な表現ではありますがそれが「当たり前」の環境で育った時、それが子どもの精神の発達に影響を与えることは想像できると思います。
恐らくですが、消極的になったり、指示されたことにだけ従おうとするなど「怒られないためにはどうしたらいいか」という状況。
あるいは「なにやっても怒られるなら、もう悪いと言われていることをやっても一緒だ」という状況を生み出しかねないですよね。
つまり、「怒る」という動作がもたらす結果として、端的に言えば自己肯定感の低下を招いてしまうわけです。
「叱る」の実践

では次に「叱る」という動作が子どもの発達に与える影響を考えてみましょう。
まず「叱る」の定義ですが、「叱る」は相手の将来を思いやり、相手を正しい方向に導く事を行動の基本としているようです。
これを前提として先ほどの例について考えていきます。
状況は同じく、テレビを見ながら牛乳を飲んでいた子供が牛乳をカーペットにこぼしてしまった。というパターンで考えていきます。
この状況が起きたときあなたならどのように「叱り」ますか?
考え方のベースは「相手の将来を思いやり、相手を正しい方向に導く事を行動の基本とする」です。
これについては答えは無限大にあると思います。
参考ですが「相手の将来を思いやり、相手を正しい方向に導く事を行動の基本」としたとき、私ならこうするであろうという例を紹介させてください。
まず私が普段意識していることは「対話」です。
感情をなるべく排除して、目をみて話をします。
(子どもの手を握って目を見ながら)
「●●くん、今テレビを見ながら牛乳を飲んでてこぼしちゃったよね?なんでだかわかる?」
「テレビを見ていることで気持ちがテレビに行ってしまってるやんね?牛乳を手に持っていることを忘れてしまうから落ちてしまうんじゃないかな?」
「テレビおもしろいよね。見たい気持ちはわかるけど、牛乳を飲むときは牛乳に集中してほしいの。そうしたらきっとこぼれないよ。」
「牛乳がこぼれてしまうと掃除が大変だからパパは悲しいの。そして牛乳がこぼれるともうその牛乳は飲めないよね?食べ物や飲み物はずっとたくさんあるわけじゃないから大切に飲んでほしいの。わかってくれる?」
とかこんな具合でしょうか。
実際に牛乳をこぼされたからと言って、最初からここまですることはないと思いますが、本当に大事な事を伝えるときは「手を握って目を見て話す」ということを実践しています。
上記で挙げさせてもらった参考意見には工夫点があるのでそこについても解説させてください。
「●●くん、今テレビを見ながら牛乳を飲んでてこぼしちゃったよね?なんでだかわかる?」
▶まずは問題行動の確認と自分で考えてもらうという工程を入れています。
「テレビを見ていることで気持ちがテレビに行ってしまっているの。牛乳を手に持っていることを忘れてしまうから落ちてしまうんじゃないかな?」
▶次にその問題行動から生じた結果への考察を話します。
子どもがAをするとBが起こるという、原因と結果のモデルが少ないのでそれを補う目的です。
「テレビおもしろいよね。見たい気持ちはわかるけど、牛乳を飲むときは牛乳に集中してほしいの。そうしたらきっとこぼれないよ。」
▶まず相手の気持ちへ共感するようにしています。そして指示ではなく希望を伝えるようにします。
また希望を実行することで得られるであろう結果の説明をします。
「牛乳がこぼれてしまうと掃除が大変だからパパ悲しいの。そして牛乳がこぼれるともうその牛乳は飲めないよね?食べ物や飲み物はずっとたくさんあるわけじゃないから大切に飲んでほしいの。わかってくれるかな?」
▶最後は問題行動を辞めてほしい理由の説明と受け入れられたかの確認をします。
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、こんな感じです。
大人でも同じだと思うのですが「理由がわからないまま非難される」って結構イライラするんですよね。
さらに言うと、そのイライラだけが記憶に残って、叱られている内容が頭に残らないんです。
(私の場合ですが…)
なので叱るときには
①問題行動の確認
②問題行動の説明
③説明を踏まえてどうしてもらいたいか
④それを実行することでどうなっていくことが予想されるか
⑤受け入れられたかの確認
⑥受け入れられたら褒める
を意識しています。
理由がはっきりしていて、子どもが納得・共感ができたときにすんなりと受け入れることができます。
逆に理由なく感情的に怒鳴られることに対しては、状況の理由が「親の感情」なので納得や受け入れができないんです。
結果として親は罪悪感を抱えた上に、子どもは受け入れができていないので状況が改善しない。
そして子どもは行動の問題個所がわからないので同じ行動を繰り返し再び怒る…というループに陥るわけです。
この時親は「怒ったのに反省していない」とか思うかもしれませんが、そもそも反省のしようがないんですよね。
子どもからしたら「牛乳を見ながらテレビをみていたことに怒っているのか」
「牛乳がこぼれたことに怒っているのか」
「牛乳をこぼしたのに自分が掃除しないことに怒っているのか」わからないわけです。
なので「怒る」というのは過程をみても結果をみても良いこと無しなんですよね。
叱るという事が本当の意味で実行されたとき子どもの精神にはどのような影響が起きるのでしょうか。
「叱る」がもたらす影響

まず「良いこと」と「悪いこと」の判断基準が形成されていきます。
なにが良くて何が悪いかを理由付きで説明していくので、それを10年積み重ねるだけでも良し悪しの判断基準の土台が身につくと思います。
さらに「自分で考える力」が身に付きます。
問題行動を確認したときに「相手や環境がなにを問題としているのか」を毎回問いかけるので嫌でも考える機会が訪れるわけです。
端的に指摘されるだけでは「考える間もなく従わされている」状況なので考える力は付きにくいですよね。
そして超大事なこととして「自己肯定感があがる」というものがあります。
上記は⑥の手順でのみ「褒める」と書いていますが、できたことやわかったことに対して日常的に褒めるといいと思います。
怒られるより褒められるほうが体感が良いことは大人も子どもも同じなので、自然と怒られる行動を避けるようになり、褒められる行動を選択できるようになります。
結果として「自分はこれでいいんだ」という安心感に繋がるため、長期的に見たとき親は怒る回数が減って、子どもの精神にも良い影響を与えることができます。
まとめ
「怒る」と「叱る」。
言葉では理解できてもなかなか実行に移すのは難しいと思います。
しかし「怒る」と「叱る」の違いを知ることや、「叱る」ことによって得られるメリットを理解することで、これからの子どもとの付き合いや精神の発達に大きく貢献できることがイメージできたのではないでしょうか。
大人とはいえ一人の人間なので常に相手の事を考えて「正しく叱る」というのは難しいと思います。
正しく叱るためには大人が精神的に成熟する必要があると思っています。
突発的に湧いてきた感情をセーブして、「相手のために」言葉と行動を選択しなければいけないわけですからとても難しい事です。
一般的には大人が子どもを育てているという感覚だと思うのですが、私は子どもによって育てられている感覚をとても感じます。
大人が精神的に成長できたとき、子どもはそれを成長で返してくれるわけです。
育児には悩みがつきものですが、子どもと同じ視点をもって接することができればもっと子育てがしやすくなるかもしれません。
それでは素敵な子育てを。