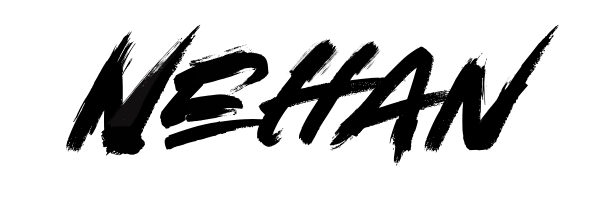みなさんこんにちは。
今回は子どもに与えるお菓子について書いていきたいと思います。
子どもってお菓子好きですよね。
できればあまり与えたくないけど、嬉しそうに食べる姿は可愛いし…でも食べ過ぎが良くないのはわかるし…育児におけるジレンマですね。
今回は子どものお菓子やジュースを与える上で気をつけた方がいいことと我が家で実践しているオススメの方法についてお話したいと思います。
1.お菓子の食べ過ぎによる影響

子どもを育てる親としてかなり気になる部分ですよね。
お菓子の食べ過ぎによってどんな影響が起こり得るのか、リスクの面で見ていきたいと思います。
①虫歯リスク
これは言わずもがなですね。なんせ虫歯になる可能性が高いです。
まずは虫歯になるメカニズムを簡単にご説明します。
主な原因は口の中に残る「糖質」と「虫歯菌」です。この二つが化学反応を起こして酸になり歯を溶かしてしまう状態が「虫歯」という感じですかね。
みなさんもご存知かもしれませんが、生まれたての赤ちゃんの口の中には虫歯菌が存在しないようです。
育児の過程で親の虫歯菌が赤ちゃんに感染して、その後赤ちゃんの口の中に虫歯菌がすみつくようになるようです。
なぜお菓子が極端に虫歯リスクを高めるかというとお菓子は口内に残留する可能性が高いんですね。
例えばチョコレートやキャラメル、チューイングキャンディなんかは歯の溝に残ったりしますよね。またスナック菓子なんかも歯の溝に残りやすいです。
お菓子を食べた後に入念に歯磨きをしても全てを取り除けるわけではないですし、お菓子の後に歯磨きの習慣をつけるのは結構ハードだと思います。
赤ちゃんの時期に虫歯菌に感染させないというのがベストですがそれもなかなか難しく、お菓子を与えることはどうしても虫歯のリスクを高めてしまうようです。
②栄養の偏りリスク
お菓子って大体15時くらいに食べますよね。
小さい子どもは胃袋も小さくて一回に食べられる量も少ないので、お菓子で間を繋ぐという方もいるかと思います。
イヤイヤ期とかでごねられてお菓子を食べさせすぎてしまったりしまうと晩御飯が食べられなくなってしまうというのはあるあるだと思います。
ただお菓子を食べすぎて晩御飯を食べられなくなるというリズムが定着してしまうと結構危険ですよね。
栄養がほとんどないお菓子でお腹を満たしてしまうような状態が継続するので努力をしてでも避けたい事態です。
③味覚形成に悪影響を与えるリスク
人の味覚は色々な味を経験して徐々に形成されていくものだと考えられています。味覚発達のピークが3〜4歳、そして10歳頃までの味の記憶がその後の味覚の基礎になるという説があります。
お菓子が好きでお菓子ばかり食べていると当然味覚形成にも影響が出てきます。
お菓子は甘いとかしょっぱい味が多いと思いますが、人は食べ慣れた味を好みますし、味覚形成の段階で偏りが生じるとその後の好き嫌いにも影響がでてくるかと思います。
食事は体を作ります。なるべく幅広くいろんな味を経験して、大人になっても好き嫌いなく生活できるのが良いですよね。
2.お菓子を与える上で気をつけた方がいいこと

それでは上記のリスクを踏まえた上でどのようなことに気をつけるべきなんでしょうか。
まず第一に生活環境にお菓子をなるべく置かないようにするというのが理想です。
さらに言うと親である私たちもお菓子から離れる必要があると思います。
我が家ではチョコやキャラメルなど歯に残りやすいもの関連はなるべく買わないようにしたり、実際にお菓子自体を親である私たちが子どもの前で食べないようにしています。妻がチョコ好きなので、食べるにしても寝かしつけが終わった後などに食べるようにしています。
ただ市販のお菓子はパッケージにアンパンマンとかがデザインされていたりして、巧みに子どもたちに接近してきます(笑)
泣いてどうしようもない時など場面によっては我が家でも普通にあげるようにしていますし、友達と一緒にお菓子を食べる場面などは特に規制はしないようにしています。
気をつけることとしてはお菓子をあげることを習慣化しないことだと思います。
子どもにとって特別なもので、親にとってはピンチの時に助けてくれる諸刃の剣くらいに考えて、うまく利用するのが良いのかな?と思います。
3.我が家で実践しているオススメの方法

そんなに大したことではないのですが、少量で小分けになっているお菓子を選ぶようにしています。
例えばラムネとか少ない量でワンパッケージが完結しているものですね。
スナック菓子なんかは一度袋を開けてしまうと食べきらないといけない気持ちになったりすると思います。
我が家ではスナック菓子を与えるときなどは必ずお皿に出して少量ずつあげるようにしています。
一袋渡してしまうと必ずと言って良いほど全て食べてしまいますし、途中で量をコントロールするのが難しくなります。
少量をお皿に出してあげて、足りないと言われたらさらに少量を「おかわり」としてあげるようにしています。
この時「おかわりは一回だけだよ?いい?」と言って本人と約束をするようにします。
一度に全部与えてしまうとその後におかわりをねだられますが、一袋の分量内でおかわりをさせてあげると満足感も高いようで比較的少量でお菓子を切り上げられます。
またジュースを与える時にも同じ方法を実践していて、コップに少しだけジュースを入れて与えるようにしています。
大人の感覚だとコップにいっぱい入れてしまいがちですが、少量で「おかわり」をさせてあげることが満足感に繋がるようです。
そうすることでお菓子やジュースの消費量も減りますし、家計的にも優しいです。
ぜひ試してみてください。
4.まとめ
いかがでしたか?
お菓子を与えることは避けられないにしても、量のコントロールはできると思います。
親が全く食べなければ子どもにとっても距離のあるものになりますし、上手く使えば育児の味方になってくれる場面もあります。
デメリットも多いですが、虫歯リスクをできるだけ避けてお菓子と付き合っていけるといいですよね。
では素敵な育児を。
| 返信転送 |