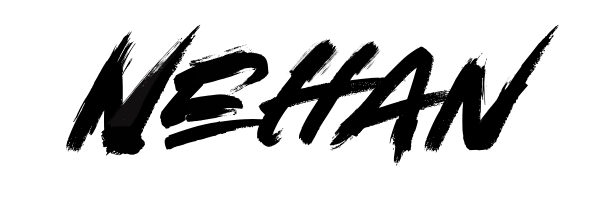みなさんこんにちは、涅槃ぶろぐのモロです。
今回は子育てについて書いていきたいと思います。
うちの双子君たちは早いもので4歳になりました。
自分たちでできることも増えてきて、いろんなことへの興味も増しているように感じます。
そんな中で「自分は子どもたちの好奇心を阻害してはいないだろうか…?」と感じたので、そこで考えたことを皆さんに共有していこうと思います。
単なる「アカン!」はアカン?

「アカン!」というのは「ダメ!」という意味です。
あたりまえのように使っていましたが、どうやら関西弁のようですね。
子育てをしていると、とっさに「アカン!」とかを言ってしまうことがあります。
例えば、熱々のお鍋に対して「これなにー?」とか言って、触ろうとしたり。
そんなとき私は「アカンで!触ったら熱いで!!」と、とっさに言うわけです。
もちろんこれは「アカン!」で良いと思っています。
だって、触るとヤケドをしてしまうわけなので。
でも、そんなに危なくないことでも忙しかったりすると「アカン」と言ってしまうこともあります。
例えば、配達員さんが荷物を届けてくれた荷物を受け取って「部屋まで運びたい!」とかです。
これは双子あるある?なのかわかりませんが、一方にそれを許可すると、もう一人も「僕もやりたい!!」と言うわけです。
我が家は2階にリビングがあるのですが、
・息子Aが2階まで荷物を運ぶ
・運んだものを親が1階まで運ぶ
・息子Bが2階まで荷物を運ぶ
という動きがもれなくセットになるわけです。
時間があるときは「いいよ~」と言って、それぞれに同じことをやらせてあげるのですが、時間が無いときはとりあえず「アカン!!」と言うわけです。
こういうとき「アカン!」の理由を「ちゃんと理由を説明してあげないとなあ」と思うんですよね。
なぜ「アカン!」のかを、大人は説明する必要がある。

物事を禁止する裏には大体において理由があります。
(危ないとか、めんどくさいとか。)
でも、その理由について禁止する側はしっかり認識していく動きと説明していく動きをとらないといけないんじゃないかと思うんですよね。
例えば「危ない」で子どもの行動を禁止するなら、すぐに説明できると思います。
でも、「めんどくさい」とか「なんとなく」で、自分の行動を規制されたらきっと子どもサイドは納得がいかないと思うんですよね。
これは私自身の経験なんですが「小学生のうちは、夜21時に寝なさい。」というルールがありました。
私は4人兄弟の末っ子で、21時を1分でも過ぎようものなら兄弟から「はよ寝ろよ。」と責められるわけです。
でも「なんで21時に寝なあかんの?」と聞いても「そう決まってるから」とか言われるわけですよ。
そこにまともな説明がないんです。
21時以降に見たいテレビがあっても、「小学生だから」と言う理由ですべてが禁止されるんですね。
私はそんなときに感じるわけです「小学生だから、なんなんだ。」と。
例えば、夜遅くに起きると「翌日朝起きれなくなる」とかならまだわかるんですよ。
(この場合「翌日しっかり起きる」という約束の上で、21時を過ぎても寝なくていいならルールとして納得です。)
でも、納得できる理由もなく禁止されると「ただ一方的に意見を押し込められている。」という感覚にしかならないわけです。
当時は家庭内にそういう「理由のわからないルール」がたくさんあったので、とにかくストレスに感じていたのをいまだに覚えています。
子どもの「やりたい!」を支える姿勢をもつこと

子どもが何かに対して「やりたい!」とかわがままな行動をとることは、普通のことだと思います。
でも親には、過去の経験や知識があるから、それに基づいて禁止することもあるし、大した理由もないのに子どもの行動を禁止してしまうこともある。
親子の信頼関係がしっかり土台にあれば、多少の「理由なき禁止」は問題ないと思うんですが、そういうことが積み重なってくると子どもは「自分の意見は通らない」という感覚を持ってしまうと思います。
これは子どもがもつ好奇心の芽を摘んでしまうだろうし、将来的にみてもなにも良いことが無いんですよね。
禁止するなら理由は説明した方が良いし、それでも子どもが納得できないなら、「条件付きの許可」や「代案」くらいは提案してあげたいと思うわけです。
(手を離さない自信があるなら、ブランコの"立ちこぎ"をしてみてもいいよ。的な。)
結局のところ、親は子ども本人の感覚を持ち合わせていないので「大丈夫かな…?」という感覚になることもありますが、何事もやってみないとわからないわけです。
最初は手を添えるところから始めて、そのうちできるようになれば子どもにとっても成功体験になるわけで、親としては子どもの興味に寄り添ってのびのびと挑戦できるサポートをしてあげたいな、と思いました。
まとめ
まとめですが、以下の二つを大切にすることが、親子両面にとって重要になると思います。
・ダメな理由を説明する(子どもではなく、人として向き合う。)
・子どもの「やりたい!」をサポートしてあげる姿勢を持つ
子どもを育てていて感じることが「親の都合で物事を判断してしまうときがある」ということなんですよね。
もちろん時間とか、親サイドの精神的な余裕も大事なんですけど、なるべく子どもには真摯に向き合いたいなと思います。
(「めんどくさい」と感じることはめちゃくちゃ多いんですけどね。)
でも、子どもも「自分の発言や行動にしっかりと向き合ってくれている」ということは感覚として理解してくれると思いますし、そういう姿勢の積み重ねが親子の信頼関係を構築していくんじゃないかな?と思うんですよね。
私もまだまだ至らないところが多いですが、精進していきたいと思います。
それでは素敵な子育てを。