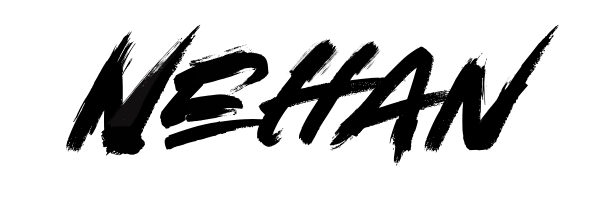みなさんこんにちは。
今回は家庭について書いていきます。
私自身、家庭ができてから3年そこらの駆け出しではあるんですが、円満家庭をつくるために必要な要素というものが見えてきたように思います。
「これから家族ができる人」や「円満家庭にしていきたい!」という人は参考になる内容だと思います。
もしよければ読んでみて下さい。
●そもそも円満家庭って…?

まずは円満家庭がどういう状態を指すのか定義していきます。
端的に言うと「仲のいい家族」ですかね。
夫婦や子どもとの関係がうまくいっている状態です。
家族という少人数の共同体でもそれを円満につくり上げていくのって結構難しいですよね。
なぜか喧嘩に発展してしまったり、なんとなくモヤモヤする出来事が多かったり…。
心身ともに近くにある存在だからこそ難しく感じる部分なのかな?とも思います。
そんな中でどんなことに気をつければ円満な家庭環境をつくれるのかをお話ししていきます。
●なぜすれ違うの…?

家族といえど喧嘩ってしますよね。
むしろ「友達とかより家族との喧嘩の方が多い」という人も多いかもしれません。
なぜ人と人はすれ違うのでしょうか。
言葉を選ばずに言うと「我の押し付け合い」がすれ違いや喧嘩に発展します。
例えばお風呂の順番とか。
「自分が先に入りたい」を2人が言い始めると喧嘩になりますよね。
1人が譲れば喧嘩にはなりません。
本当に当たり前の話なんですけど、日常の中だと結構忘れがちです。
さらに言うと「正しさの押し付け合い」も喧嘩やすれ違いの原因です。
共働き家庭とかで「どちらが家事をやるべきか」とかがこれにあたるように思います。
「私の方が収入があるから」とか「私の方が労働時間が長いから」などで
「仕事の負担が少ない方がやるべき」とか「経済的貢献度の低い方がすべき」というような
考えを相手に押し付けるとすれ違うのかな?とか思います。
円満家庭の考え方で大事なのは「支え合い」だと思います。
仕事の負担感なんかは相対的なものなので、絶対的な共通認識では計れないですよね。
例えば仕事自体はそんなにキツくなくても人生で一番嫌いな人が職場にいて
毎日かならず関わらないといけないとなったときに負担感は上がります。
つまりは自分の事情を押し付けるだけになってしまった時に人はすれ違ってしまうわけです。
●どうすればすれ違いを減らせる?

常にそれができるかは別にして「相互理解」と「歩み寄り」があれば人とのすれ違いは減らすことができます。
共働き夫婦での家事負担を例にしてみます。
夫婦でどちらが家事をするかという言い争いになった時
「俺の方が稼いでる」とか「私の方が労働時間が長い」という言い争いがあったとして、
どのように「相互理解」と「歩み寄り」をすればいいのかという話です。
まずは「相互理解」から。
結論的な「どちらが家事をするか」という問題は置いておいて、
自分が「今どんな負担を感じているか」と「今自分が家庭のためにできること」を話し合います。
例えば「今仕事で大きなプロジェクトを抱えているから家事負担がきつい」なら
「現状」どれだけ家事負担ができるかを話し合います。
プロジェクトはいつか終わるわけなので、パートナーからしても
「一時的な負担」と割り切ることができます。
「これから死ぬまで家事は全て私がするもの」と暗黙のうちに決まってくると
精神的な負担がかなり大きいですよね。
そのほか「職場に超嫌いな上司がいてそれが負担感を強めている」なら、
上司がいなくならない限り日常的な消耗が軽減される未来は見えてこないわけです。
こうなってくると転職とかそんな話が出てくるわけですが、
転職をすることでストレス要因が排除できるなら迷わずそうすべきですよね。
そうなったときに必要なのは「職場を変えられようにパートナーを支える」です。
そうすることで長期的に見て自分の家庭内での負担感を減らすことができます。
歩み寄りの部分で言うと「できるだけはちゃんとする」というところが大事だと思います。
「まあ、俺も家事ができないことはないけど今までやってくれてたし俺の仕事じゃないわな〜」とか言い出すと喧嘩になりますよね。
考え方のベースとしては「自分が楽をする」ではなくて
「自分に何ができるか」が大事だと思います。
結局のところ目先の労力をケチって家庭内がギスギスしてくる道を選ぶか
腰は重いけどしっかり自分にできることをやって家庭内を円満に作り上げていく道を選ぶか
という2択になるわけです。
子どもがいる家庭で親が目先の労力をケチる方に進んでしまうと、子どもは日常的にその光景を目にすることになるので
「夫婦ってこういうものなんだ」という認識が土台部分に植え付けられてしまいます。
なので円満家庭を気付くためにはまず夫婦で支えあう姿勢を見せることや、
円満な夫婦関係を作り上げていく必要があります。
それができるようになれば家庭内に思いやりの基礎が出来上がるので、
子どもにもそれが引き継がれていくという考え方です。
●まとめ
円満な家庭をつくるためには自分本位ではなく、
家庭本位な行動を日々継続することが大切だということだと思います。
「考えたらわかるわい」みたいな話ですが、それが「できるかどうか」はまた別の話です。
一時的な行動で「やってる」ではなくて、
日々の生活から継続していくことの重要性をお伝えしたかったわけです。
家庭という小さなコミュニティですが、そこから学ぶことは本当に多いと思います。
また日々の気付きがあれば共有させてください。
それでは素敵な人生を。