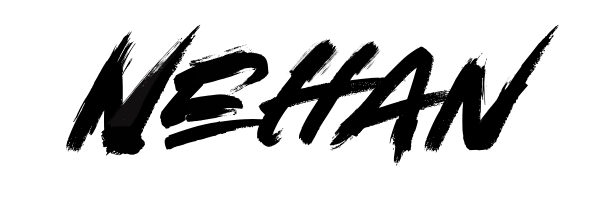みなさんこんにちは。
今回は子どもに食べさせるお菓子の話です。
我が家は平日ほぼ毎朝、歯磨きのタイミングで子どもにyoutubeを見させています。
その中で海外のyoutuber?が青とか緑とかのカラフルなお菓子を食べていて、息子が「これ食べた〜い!」と言っていたのがきっかけで、この記事を書くに至りました。
大人になってから見るお菓子

息子の「これ食べた〜い!」を聞いて、「(え、これ見て食べたくなるか…?)」と思いました。
まず第一に感じたのが「体に悪そう」だということです。
そしてその後に感じたのが「美味しくなさそう」でした。
でもよくよく考えてみると、昔の自分はこの手のお菓子を「食べたい」と感じていたように思いました。
ベロが赤とか青に変わるガムとか、なんか超デカいカラフルなペロペロキャンディーとか。
そう思うとおいしそうで食べたいとかよりも「これがどんなものなのか試してみたい」という感覚なんだろうな、と思いました。
このお菓子は食べさせるべきなんだろうか…?

その上でなんですけど、そのカラフルな体に悪そうなお菓子を息子に食べさせるかどうかを考えました。
うーん…難しい。
とにかくこの手のお菓子はべらぼうに甘いわけです。
このべらぼうな甘さを息子が「美味しい」ととるか「甘すぎる」ととるかは未知数なんですよね。
でも興味には向き合わせてあげたいと思っています。
それがどんなものかわからないまま、理由もわからないまま禁止されるのは、きっと子どもにとっては良くないはず。
そういう意味で、私は息子にそのお菓子を食べさせてあげたいなと思いました。
というかよくよく考えると、普段からそんなにお菓子を食べる習慣がないので「お試しで食べてみる」くらいはいいだろう、とか。そんなことも思いました。
常にそのお菓子を食べる習慣がつくと、体にも精神にも悪そう(あくまでイメージです。虫歯とか糖分の取りすぎとか…)なので良くないと思いますが、大人がそうならないようにルール作りをしてあげれば問題ないように思いました。
興味に向き合える環境づくり

私は息子たちの子育てを考える上で、興味にしっかり向き合える環境は用意してあげたいなと思っています。
それは例えば、車が好きなら車をたくさん見れる場所や本を与えてあげるとか、物事を調べる手順を、自分が持っている手札の中から教えてあげるとかそんなことです。
「物事を調べる」という動き一つとっても、「スマホで調べる」とか「図鑑をめくる」とか「実際に見に行く」とかいろいろあるわけです。
百聞は一見にしかず。
百見は一触にしかず。
百回言葉で聞くより見た方がいいし、百回見るより一回やってみたほうがわかることが多いと思っています。
(「百見は一触にしかず」という言葉があるかは謎ですが)
とにかく息子たちの見聞を広めるために、実際にいろいろと体験させてあげられる環境を用意したいと思っているというお話でした。
まとめ
大人になると「体に悪いから」みたいな理由で、子どもの興味にネガティブになってしまうことがあるんだな、と思いました。
昔は自分もいろいろ試してみたいと思っていたはずで、「体に悪いから」とか言われても納得できなかったと思います。
例えば極端な話「その一触が人生を壊してしまう」というような危険性がなければ、いろいろ試させてあげてもいいのかな?と思いました。
「ビルの7階から飛び降りてみたい!」とか言われても、それは試させてあげられない。みたいなことですね。
代わりにバンジージャンプとかはできるかもしれませんし。
私も好奇心旺盛な方だと思うので、息子たちの興味にはなるべく寛容でありたいなあ、と思いました。
誰かの子育ての参考になれば幸いです。
それでは素敵な子育てを。